今日、台所用石けんを作っていてふと気になったんです。
「そういえば昔の人は、どうやってお皿洗ってたんやろ?」って。
せっかくなので、日本の台所の歴史をちょこっと旅してみました。
1. 江戸時代〜明治のはじめ:灰汁と米のとぎ汁の知恵
日本の台所は、米と野菜と魚が中心で、油の少ない食生活でした。そのため、食器洗いには主に「米のとぎ汁」や「灰汁(あく)」が使われていました。
灰汁は木灰を水に溶かしたアルカリ性の液体で、油汚れを分解する力があり、ぬかと共に昔ながらの洗浄の主役でした。
世界の石けんの始まりも「灰」から
実は、世界の石けんの始まりもこの「灰」と関係しています。古代ローマの「サポーの丘(Sapo Hill)」では、獣の脂と木の灰が偶然混じり合って石けんが生まれた、という有名な逸話が伝えられています。
つまり、日本も世界も、「灰」から清潔の知恵が始まったんですね。

2. 明治〜大正:西洋文化と石けんの出会い
明治のころ、西洋文化が入ってきて陶器やガラスの食器が広まりました。
バターや肉を使った料理も増えて、油汚れには「石けん」が欠かせなくなります。
フランスのマルセイユ石けんや、ドイツのブラシ文化も紹介され、日本の台所に少しずつ取り入れられていきました。
3. 昭和前期:戦時下の石けん不足と暮らしの知恵
昭和のはじめごろも、台所ではまだ石けんが主役でした。
けれど戦争が近づくにつれて、石けんの原料である油脂は、爆薬の原料となるグリセリン製造にも使われたため、戦時中は極端に不足し、十分に行き渡らなくなります。
そのため、米のとぎ汁や灰汁をもう一度使ったり、石けん代用の粉を工夫して使ったりと、暮らしの知恵で困難をしのいでいました。
4. 昭和中期〜後期:合成洗剤の時代へ
1950年代:戦後復興と技術導入
戦後しばらくの台所は、まだ石けんが主役でした。この頃、日本にアメリカから合成洗剤の技術が導入され、研究や製造が始まります。
1960年代〜:台所の主役交代
戦後の復興が進み、暮らしが豊かになっていくと、台所にも大きな変化が訪れました。揚げ物や肉料理が日常に増え、ステンレスやプラスチックの食器も一般的になります。
この時期に登場したのが「合成洗剤」と「スポンジ」です。テレビCMなどの影響もあって爆発的に普及し、「泡で油を落とす」という新しい価値観が広まることで、台所文化は一気に変わりました。
合成洗剤がもたらした課題
便利さの影で、手荒れや環境への負担を心配する声も聞かれるようになります。
たとえば、琵琶湖などでの富栄養化問題が、洗剤中のリンを含む成分と結びつけられ、業界全体で「リンを減らした洗剤への切り替え」が進んだ歴史があります。
5. 平成〜令和:シンプルな道具への回帰
いまの日本の食卓は、世界中の食材で彩られています。豊かになった一方で、改めて「シンプルな洗い方」への回帰も始まっています。
固形石けんや棕櫚たわし、セルローススポンジなど。昔ながらの道具が、現代の暮らしに合った形で見直されているのです。
大切にしたいこと
食文化が変われば、洗い方や道具も変わります。でも、どの時代でも共通しているのは、「大切な資源を、無駄にせず、感謝していただく」こと。
小多福堂は「犠牲にしない」選択を大切にしています。犬の皮膚を犠牲にしない、環境を犠牲にしない。そして台所でも、資源を大事にしながら清潔に整えたい。
白い石けんがひとつ台所にあるだけで、暮らしはちょっと優しくなる。そんな風景を、日本の台所に届けたいと願っています。
さて、私も食器を洗います。
参考文献・資料
・『石けん百科』(NPO法人石けんの会)
・環境省「合成洗剤と水環境」資料
・滋賀県「琵琶湖の富栄養化対策の歩み」
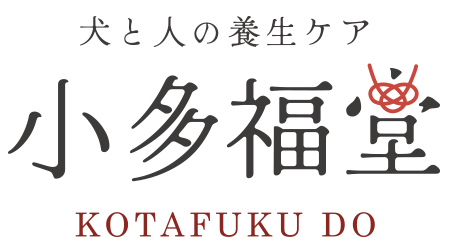



コメント